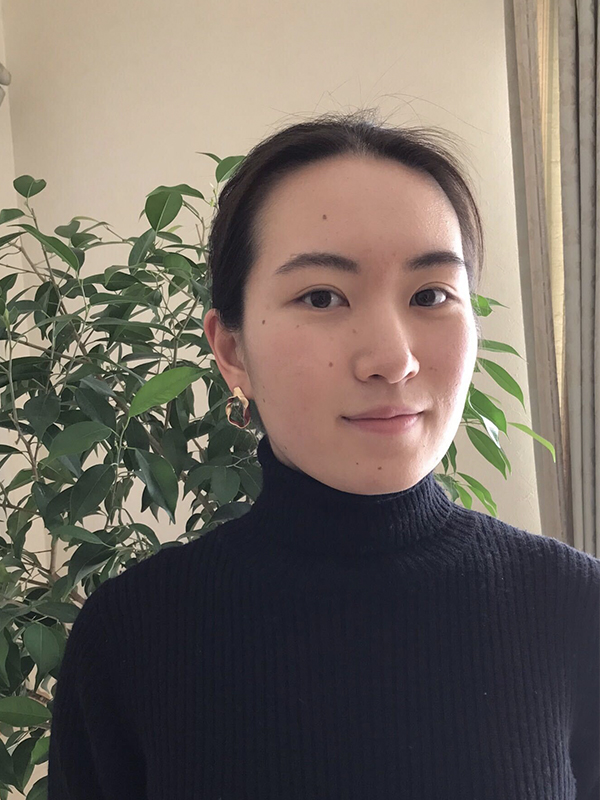2020Goldsmiths BA Designでの卒業制作展の合間、そして終わってからの数日間、ずっとこれまでの道筋を振り返っていました。卒業シーズンのノスタルジーな雰囲気に晒された影響もありますが、何より、私が卒業制作展で発表したプロジェクト「Idiolect Teachers」が、ちょうどGoldsmithsでやってきたこと全ての総集編のように感じるのです。「Idiolect Teachers」の制作過程を思い返すと、自然とBAを始めたばかりの頃や、その前のFoundationコース、時にはそれに繋がる中高生時代や幼少期まで遡って思いを巡らせてしまいます。

江副記念リクルート財団のリクルートスカラシップに申し込んだ当初は高校三年生でした。普通科の高校に通っていましたが、アートとデザインが好きで知識はあったので、自分がこの先分野を跨いで組み合わせるような実験的なデザインを探求したいという意志が定まっていました。しかし、当時掲げていた目標は「人を動かすデザインをつくりたい」というボンヤリしたもので、まだどんなデザインが広報の枠を超えて人の心を「動かす」のか、よく理解していませんでした。
リクルートスカラシップの面接で尊敬する塩田千春さんに初めてお会いでき、更に同じくアート部門審査員の秋元雄史先生・林千晶さんとのご決断で当財団の48期奨学生に選出して頂いたことで自信がついた私は、そのまま進学したGoldsmiths University of Londonのデザイン科のFoundationコースに集中し、良い成績で修了できました。スカラシップのおかげで金銭的余裕もあり、アルバイト等はやらずに学業に集中できました。しかし、同大学のBA Designに進級後、順調に成績が伸びていく反面、自分の本当のデザインの方向性や意志がボヤけてしまうという致命的な壁に当たりました。リクルートスカラシップの2度目の更新審査で作品「Primary Shrine」をプレゼンし、林先生から「これでは人の心は動かない」と厳しいコメントを頂いたのをまだ覚えています。「Primary Shrine」は初め、私の神道への興味と社会問題発見・解決を結び付けてみようと意気込んで始めたプロジェクトだったのに、締切と成績に気を取られ、肝心の社会問題も自分のスタンスも定められないまま終わってしまいました。「心が動かない」という反応はごもっともです。悔しい思いをしましたが、核心を突かれてハッとした事で自分の意志と向き合う決意ができました。更新審査や他様々なイベントを通じて、今現役で活動している人々と意見交換をできる環境も、江副記念リクルート財団奨学生の大きな利点だと思います。
壁を乗り越えたきっかけは、Michelle Williams Gamakerというアーティストとの出会いでした。元々BA Design 2年次の一環でインターンをこなす必要があり、Michelleは当時撮影していた短編映画作品の現場で仕事の機会を提供してくれたのです。撮影そのものも大変勉強になる体験でしたが、そこで繋がり、制作終了後も続いている人々との関係性こそが私を成長させてくれました。Michelleの周りにはアクティビズムに取り組む人など何らかの主張や強い意志を掲げて活動している人が多く、映画撮影の合間にも自分の視点を鋭く保つ訓練やその伝え方、インプットの仕方など、私に不足している技術をどんどん浴びせてくれました。そして皆、人間として憧れるような人々ばかりなのです。撮影中はもちろんのこと、一緒にご飯をたべている時や、出かけている時、バスでのふとした会話の中でも、「あ、私こうなりたいな」と感じる瞬間が何度もありました。常に他人の努力を笑わず、自分の意志を譲らず、こだわりを妥協しない姿勢は、いちクリエイティブとして必須で、こなしていれば私生活にも滲み出てくるものなのだと学びました。そんな皆と関わっていると私ももっと発信がしてみたくなり、自然と自分ならではの視点・自分の人生と経験に基づいた意見について考える事が増えました。
卒業制作作品の「Idiolect Teachers」は、そういった学びの積み重ねから生まれました。「私が幼少期アメリカに渡って英語を学んだ時、一番大事だったのは音だった」という経験に基づき、人それぞれ違う英語の発音と文化的帰属意識をテーマのプロジェクトです。ひたすら私が色々な人からその人個人の発音(=idiolect)を教わる動画を撮影し、そこで説明される細かい舌や唇の動きを冊子にまとめて見やすくしました。どちらも英語を外国語として話す・又は訛っている人を対象にしていて、それらを「間違った」「変な」発音ではなく、母国語や地元の訛りの技術を応用した高等芸当であることを証明しています。添付した画像は、卒業制作展での展示風景です。

「Primary Shrine」を含むBA Designの作品は、いつも「コミュニケーション手法」をモチーフにしていました。「Primary Shrine」制作当初はスピリチュアルな角度にハマっていましたが、今回は直接的に人間の言語をモチーフにしています。Michelleの影響で自分のアジア人としてのアイデンティティについて発信してみたいと感じて「文化的帰属意識」をテーマにし、自分の経験と視点に結びつけるため「発音」にフォーカスを絞り、またマルチリンガルの「言語と言語の間」の微妙な揺れ動きを追求しました。展示では教授や来場者に何度も「very real(すごくリアリティがある)」「touching(心に触れられる)」とコメントして頂けて、「moving(心動かされる)」にかなり近づけたような気がしています。まだまだ未熟な点はありますが、「Idiolect Teachers」はGoldsmithsでの今までの経験が伏線のように回収されていて、自分らしいプロジェクトになりました。
今後はしばらく言葉を使って自分の発音や文化的帰属意識について制作します。そのため、Goldsmiths卒業後はRoyal College of ArtのMA Writingコースに進学します。エッセイや評論を中心とするアカデミックなコースですが、学校の特色状アーティストやデザイナーの学生が多く、文章の発表媒体は紙に限らず詩・映像・展示等、広くクリエイティブな環境です。また、文章執筆にはかなり直接的に自分の立場の考察と明示が必要になってくるので、Michelleと知り合ってからようやく深まり始めた自分の思想を更に磨けるだろうと期待しています。その先の未来も言語・あるいはコミュニケーションを主なモチーフとし、言葉とデザインの中間地点で制作してみたいと考えています。現在は異文化が頻繁に混ざり合い、発表の機会も多いロンドンで制作していますが、将来は日本でも制作・発表を続けていくことを視野に入れています。

当財団に奨学生として所属している間ずっと、自分が一番年下でヒヨッコだという感覚がありました。冒頭でもお話しした通り、新規奨学生として申請した時高校生だったせいもありますが、アート部門の同期奨学生が多くの場合大学院生で年上だったので、無意識のうちにどこか気後れしていたのかもしれません。でも、私ももうGoldsmithsを卒業し、財団奨学生として最後のレポートを書く段になっているという事に、感慨深いものがあります。今後の後輩へメッセージを送るならば、「どうか江副記念リクルート財団の同期奨学生たちや財団事務局の皆さんを頼ってください。特に江副記念リクルート財団の事務局及び審査員の皆様は、奨学生を信じて見守ってくださいます。自分から発信さえすれば、かなり暖かく対応していただける環境なので、必要な時は手を伸ばしつつ、頑張ってください」と伝えたいと思います。