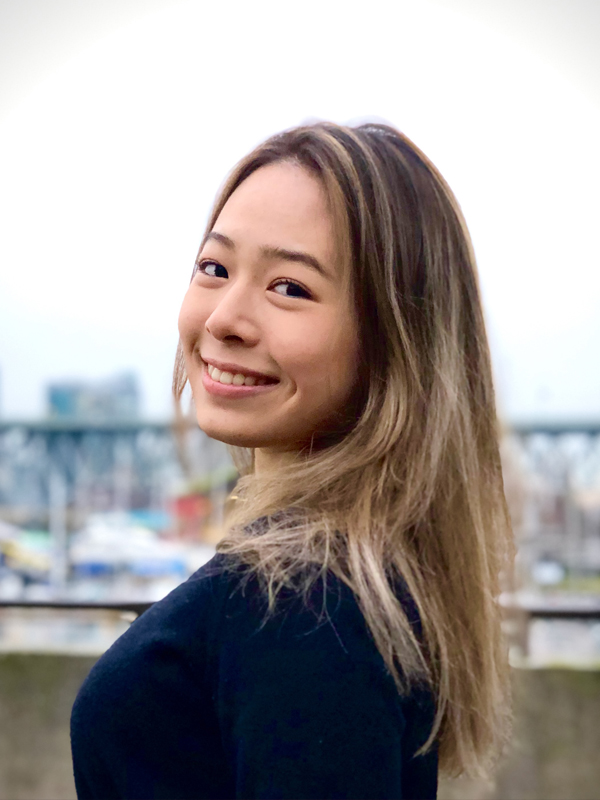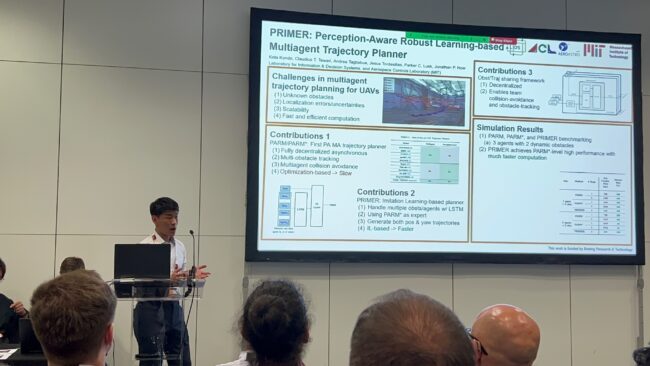大学入学当時は脳伝達物質が認知機能においてどのように働き、どのような影響を与えているのかについて学び、いずれは基礎研究を行う道を進みたいと思っていた。しかし、教授や博士課程のTA達と話すうちに、研究者が助成金の応募にかける時間の多さに驚き、資金調達が研究を進める上で大きなボトルネックになっていると聞いたことをきっかけに、基礎研究の価値をより多くの人に認めてもらうにはどうしたら良いのか考えるようになった。
そこから基礎研究で得られる知見をどのように現代社会に応用できるかのプロセスに目を向けるようになった。さらに、プロセスの効率を上げ、社会に還元するまでの時間を短縮し、社会が受ける恩恵に基礎研究の貢献が大きいという認識を社会で広めるにはどうしたら良いのかに対し興味が芽生えた。この点については、研究室で実際に研究に携わったことやスタートアップから中小企業まで様々なステージの会社でのインターンシップを通して探求した。また、自分の起業への試みを通して学び続けている。
分野としてはやはり認知神経科学が好きで、最新の研究結果を現代社会に利用できる形へ応用するツールとしてコンピューターサイエンスに着目した。そこでHCI(Human Computer Interaction)の講義を受講し、これこそ自分が学びたかったことだ!と思った。そこで、認知神経科学とHCIの講義を中心に3、4年次の受講スケジュールを組んだ。
学部生活を振り返って見ると、認知神経科学とHCIの二つの土台は十分に築けたと思うが、本当に学びたかったそれらのかけあわせに辿り着くには4年間は短すぎる期間だったため、修士課程を通して学びを深めたいと思う。
また、学部生活中に論文を出版することと起業するという2つの目標を掲げてきた。大学1、2年次はアカデミア方面に集中した結果、3年次に論文出版は達成できた。インターンシップのため1年間休学した後には、起業にフォーカスを置いた。2回の挑戦をし、アイデアからビジネスを作り出すノウハウ、そして人脈も得られた。今後も挑戦し続ける予定だ。今後の進路としては、まずカナダで数年間働きながら起業のチャンスを伺い、経験を積み業界ノウハウを得た後、20代後半で修士課程に進みたい。
財団の支援があったからできたことは多くの点が挙げられるが、最もインパクトの大きい点を挙げるとしたら、アカデミアに入るために登竜門的な存在である研究室でのボランティア活動ができた点だ。
多くの学生は生活費を稼がないといけないため、給与の発生しないボランティアのポジションを受ける金銭的余裕がない。
しかし、アカデミアに入りたい場合、研究室でのボランティア経験はその第一歩となることが多く、その後のポジションに繋がる非常に大切な経験となる。そのため、ボランティア活動をする金銭的余裕がないと大変不利になってしまう。私の場合は、財団の支援があったからこそボランティア活動に取り組むことができ、その結果アカデミアに入り、論文の執筆・出版に繋げることができたと共に、今後アカデミアに戻る道も確保できた。出版論文があるだけで、修士課程の受験がだいぶ有利になるため、今から振り返ってみると財団の支援が多大な影響を及ぼしていると感じた。
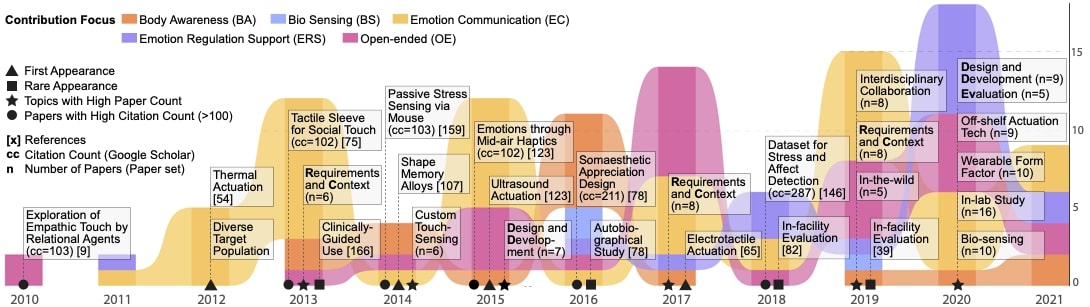
学部生活で多くの気づきがあり、自分のマインドセットが変わり、その結果、自分の行動に変化がいくつも生まれた。具体的には以下の通りだ。
• 自己省察を定期的に行うようになっただけではなく、毎日習慣的に行うようになった。その結果自分の中でプライオリティを決め・明確にし、それに従って行動するようになり、意図的にアクションを起こすことができた。
• 自分がやりたいと思うことが本当に自分のやりたいことか、それとも他人に思わされていることなのかを認識できるようになった。そして、自分がやりたいことに集中し、「やるべき」と信じるものを遂行する勇気がついた。
• 他の人はそれぞれの背景があって考え方も違う。それに対応したソリューションを提示できるようになった。気持ちを言語化し、人の気持ちやモチベーションを理解し、大切にすることで感情知能(emotional intelligence)が向上し、外交的になり、人へアプローチするのが簡単になった。
• 自分の特技や特徴が活かせ、また自分が評価される環境に身を置くことの大切さを意識するようになった。人はいずれにせよ、自分に影響を及ぼすものだ。だから私は、尊敬できる人、そうなりたいと思う人に囲まれて、その影響を少しでも受けたいと思う。
• 体調管理(フィジカル、メンタル、エモーショナル)も自分の責任と考え、高校生の時以上に気を使うようになった。
• 何かを手放すことは勇気がいることだが、自分にとってより良いもののためにスペースを確保するためには必要なことだと考えるようになった。
このような気づきをするようになったこと自体、またそれらに基づいて自分の行動を変えられるようになったことが一番の成長だと思う。
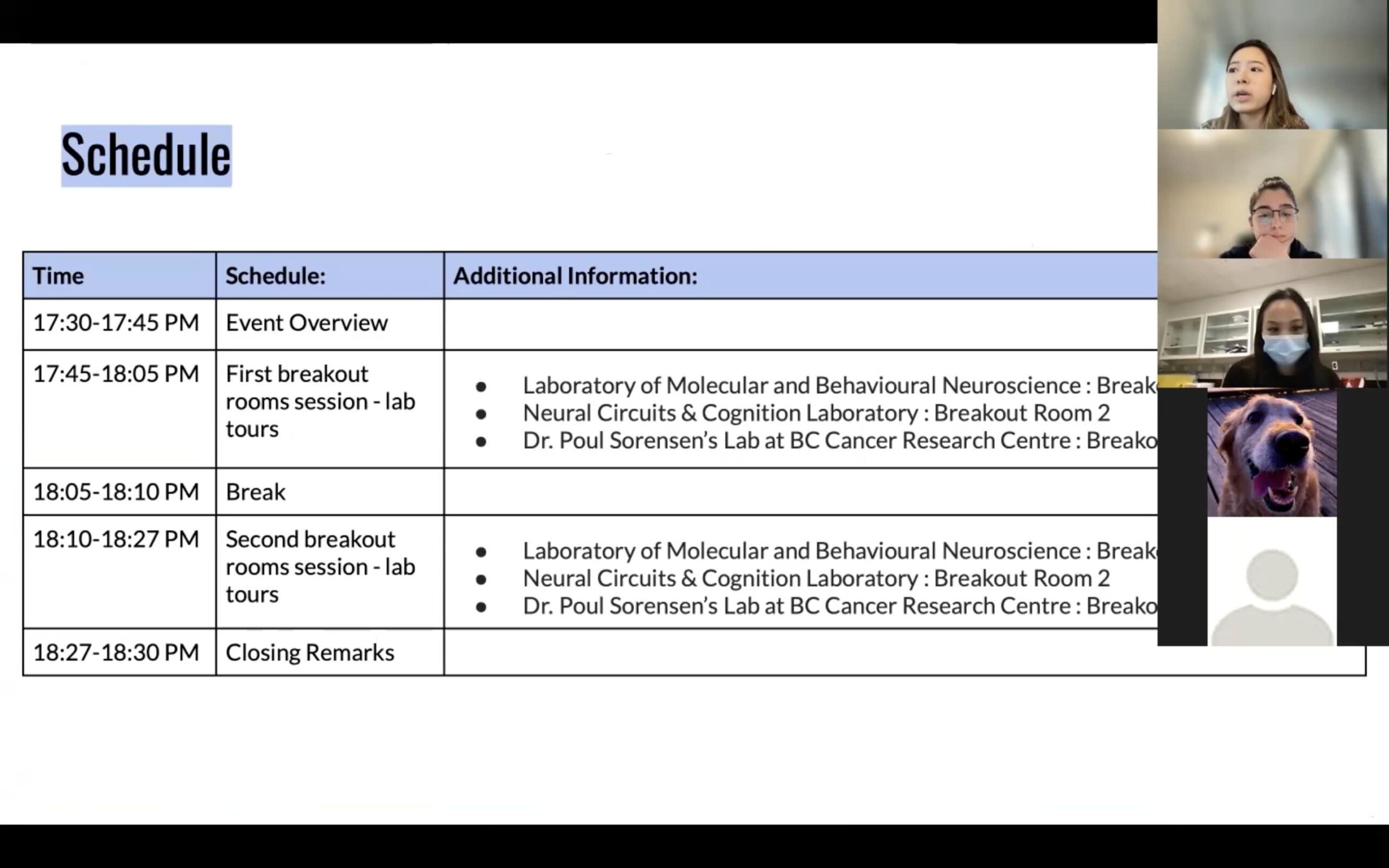
後輩たちへのメッセージ
多方面で頑張っている中、時間を見つけるのは難しいかもしれないですが、自分の進みたい方向を見定める時間を設けることは充実したな学部生活、そして人生を送る上でとても大事だと思います。自分にとって本当に大切なこと(価値観、目標など)に気付き明らかにすること、またそれに従って行動することにはそれぞれ異なる難しさがあります。簡単なことではありませんが、私にとって大事なことに基づき生きている時に幸せだと感じました。
自分にとって大切なことを明確にする上で、その行動を行いなぜ幸せだと感じるのか考えることもヒントになります。他人に教えられた価値観において「幸せ」でも、それは自分にとっては当てはまらないこともあります。自分の捉え方によって世界の見え方は全く違うものになるし、そもそも自分の視点を変えることで異なる受け取り方をすることもできます。自分の中の物差しを知覚し、何を持って幸せとするのか理解することが重要だと思います。
是非、自分が幸せになれること(好奇心を満たすなど)を優先してみてください。結局は自分のマインドセットの持ちようで何もかも変わるので、学部生のうちに少しでも自身の理解を深めてみてはどうでしょうか。